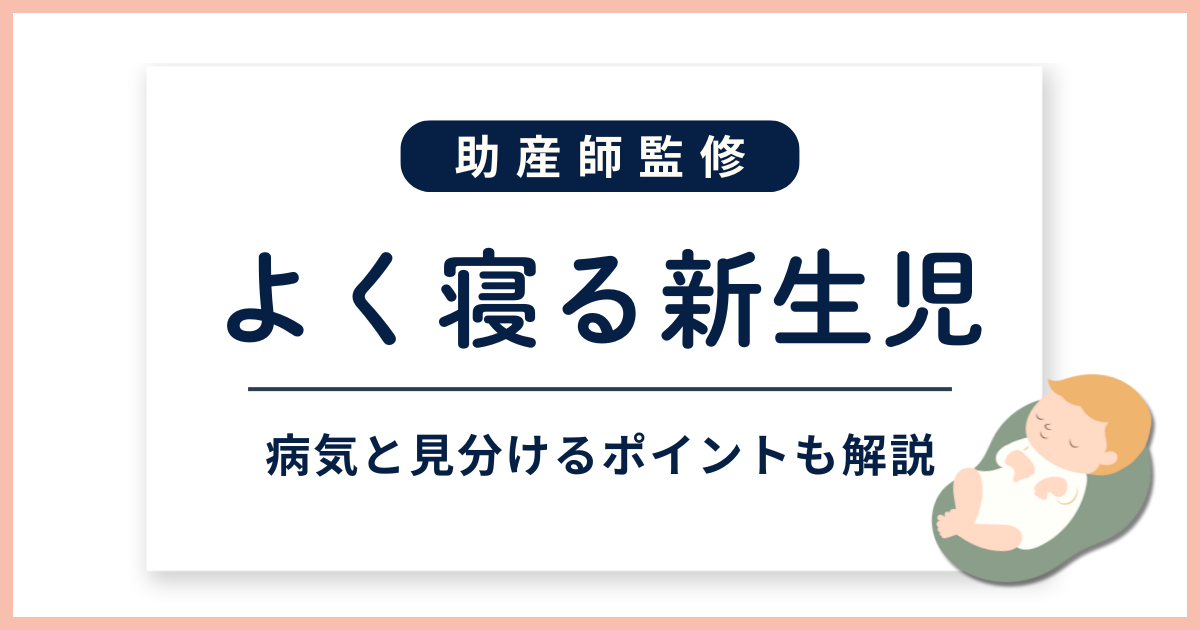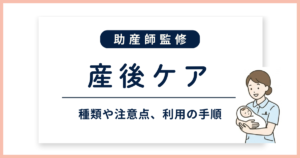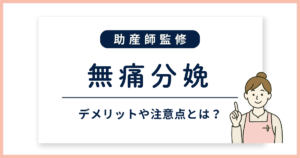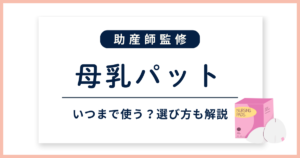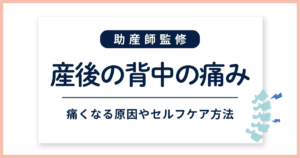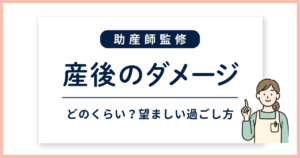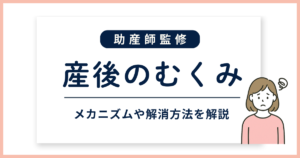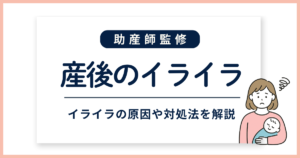我が子がぐっすり眠っていると「こんなに寝て大丈夫かな?」と不安になることもあるでしょう。
睡眠は赤ちゃんの成長に欠かせないものであり、よく寝ていても基本的には心配いりません。ただし、新生児のうちは体調不良のサインや授乳間隔に気をつける必要があります。
本記事では「新生児」を対象に、よく寝る理由や病気と見分けるポイント、起こして授乳すべき目安について解説します。
赤ちゃんの眠りを安心して見守るための参考にしてください。
新生児がよく寝るのは普通のこと
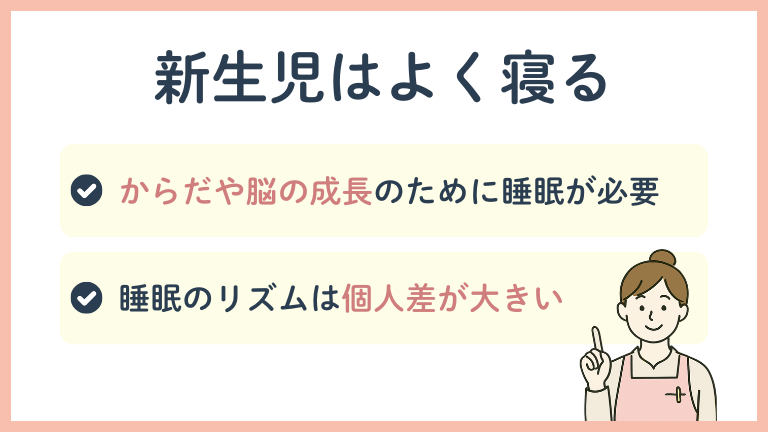
新生児はからだや脳が急速に成長するため、たくさんの眠りを必要とします。
昼夜関係なく寝たり起きたりを繰り返しますが、睡眠リズムは一人ひとり異なります。日中によく寝る赤ちゃんも珍しくありません。
新生児の睡眠リズム
新生児とは、生後28日未満の赤ちゃんのことです。一般的に新生児期は1日に16〜20時間ほど眠り、寝たり起きたりを繰り返す「こま切れ睡眠」をします。
新生児は体内時計が未発達であり昼夜の区別がまだついていないため、まとまった睡眠がとれません。ほとんどの場合1〜2時間起きては3〜4時間眠る短いサイクルを繰り返します。
ただし個人差が大きく、授乳の時間以外寝てる子もいれば、夜は何度も起きるのに午前中はよく寝る子もいます。
周りの子と違う睡眠リズムに不安やつらさを感じるママもいるかもしれませんが、よく寝ること自体は健やかに成長している証です。心配しすぎず、自然に睡眠リズムが整っていくのを待ちましょう。
新生児がよく寝すぎる場合に考えられる原因と病気
新生児がよく寝るのは、さまざまな機能が未熟で発達途中にあるためです。
新生児期特有の原因や考えられる病気について知っておくと、焦らず見守ることができるでしょう。
新生児黄疸
新生児がよく寝る原因のひとつに、新生児黄疸があります。
新生児黄疸の多くは生後4〜5日目にピークを迎え7〜10日ほどで自然と消えますが、生後3週間ほど長引く赤ちゃんもいます。新生児黄疸になるとビリルビンを処理するために体力を使い、赤ちゃんは疲れてよく眠るようになるのです。
母乳育児の場合は、母乳性黄疸が生じることもあります。母乳性黄疸も病気ではなく生後2〜3ヵ月にはおさまりますが、長引く場合は注意が必要です。
よく寝るとともに皮膚の黄色みが強まる場合は、速やかに医療機関を受診してください。
自閉症スペクトラム
自閉症の子はよく寝ると聞いたことがあり、心配な人もいるかもしれません。
自閉症スペクトラムとは発達障害のひとつです。言葉の発達が遅れたり特定のことに強くこだわったりするほか、睡眠のコントロールがうまくいかないことも特徴とされています。
実際に自閉症の子どもの5〜7割に、次のような睡眠障害が報告されています。
- 寝つきが悪い
- 夜中に目が覚める
- 昼寝が多い など
ただし寝すぎるだけでは、自閉症かどうかは分かりません。自閉症は言葉や行動の特徴があらわれる3歳以降に診断されるケースが多く、新生児期は医師でも見分けがつかないものです。
過度に心配しすぎないようにしましょう。
参考:
参考:堺市|睡眠の問題
ただの寝過ぎ?病気?見極めのポイント
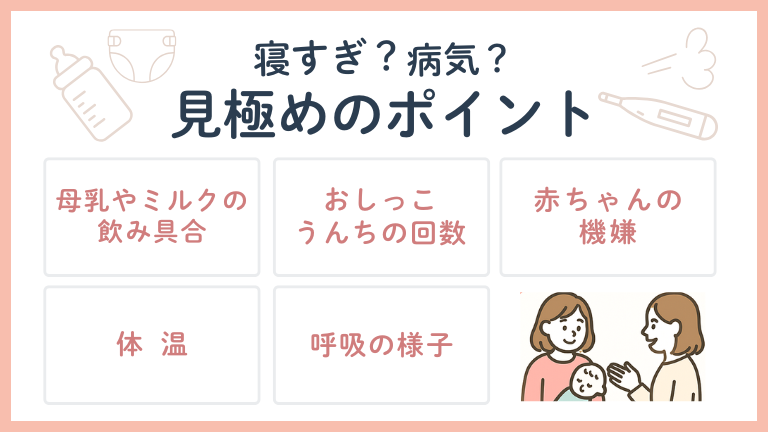
万が一赤ちゃんに病気が隠れている場合には、よく寝る以外にもサインがあらわれます。
病気を見極めるために、次の5つのポイントをおさえましょう。
母乳やミルクの飲み
赤ちゃんが母乳やミルクをよく飲めているかは大切なチェックポイントです。いつも通りに飲めているのであれば、よく寝ていても満腹の証拠と考えられます。
【赤ちゃんが十分に母乳やミルクを飲めているサイン】
- 1日に少なくとも8回授乳している
- 飲みたいだけ飲んでいる
- 肌のハリがある
- いきいきとして元気
飲む量が少なかったり、元気がなくぐったりしている場合は、念のため医療機関に相談してください。
参考:産後2週間を過ぎたママのための「授乳のギモン解消ガイド」
おしっこ・うんちの回数
おしっことうんちの回数によって赤ちゃんの水分・栄養状態がわかります。
新生児の排泄回数は、おしっこが1日10〜15回、うんちは3〜5回程度が目安です。ただし個人差もあるため、いつも通り排泄していればよく眠っていても心配いりません。
おむつがなかなか濡れなかったり、便が出にくかったりする場合は脱水の危険があります。脱水になると赤ちゃんは眠りがちになります。
「脱水かな?」と思ったら、3時間おきの授乳でしっかり飲んでもらうようにしましょう。それでも症状が改善しないようであれば医療機関に相談しましょう。
赤ちゃんの機嫌
赤ちゃんの機嫌や動きにも注目しましょう。
赤ちゃんはお腹が空いたりおむつが濡れたりすると泣きます。そして、不快感が解消されるとご機嫌になります。
手足を元気に動かしたりママの顔をじっと見つめたりすることは、体調がよいサインと考えてよいでしょう。
一方で、いつまで経ってもぐずり続けるときは、何らかの不調があるのかもしれません。明らかにぐったりしている、元気がないといった様子がある場合は、早急に受診してください。
体温
新生児の平熱は36.7〜37.5℃の範囲であり、38℃以上の発熱は病気が疑われます。
泣いた直後や授乳後は体温が上がりやすいため、赤ちゃんの体調不良が気になったら授乳前やよく眠っているときに測りましょう。
落ち着いた状態で37.5℃を超えていても、赤ちゃんが元気そうな場合は、まずは室温や衣類を調整してみてください。
新生児は自分で体温を調節できないため、室温や衣類の影響で体温が上がっていることも考えられます。
呼吸の様子
呼吸の回数や音にも注意しましょう。
スヤスヤと静かに眠っていれば十分に酸素を取り込めています。
ゼーゼーしたり苦しそうな呼吸をしていたりする場合、何らかの病気のサインかもしれませんので、速やかに受診してください。
新生児がよく寝るときは起こして授乳すべき?
病院で3時間毎に授乳するように習うこともあるため、赤ちゃんが寝てばかりいると、授乳のタイミングに困るママもいるでしょう。
基本的に体重が順調に増えている赤ちゃんであれば、ぐっすり寝ているところを無理に起こす必要はありません。
ただし新生児のうちは、授乳間隔の空けすぎに注意しましょう。
新生児の間は、授乳間隔を空けすぎない
新生児期は、前の授乳から4時間以上したら一度起こして授乳しましょう。授乳間隔が空きすぎると、脱水や低血糖を引き起こすおそれがあるためです。
特に小さく生まれた赤ちゃんや体重増加がゆるやかな赤ちゃんは、最長でも4時間ほどの間隔にしてください。成長に必要な母乳・ミルクの量を飲めなくなる可能性があります。
とはいえ、1日に1回くらい4時間以上間隔が空いてしまったくらいで心配する必要はありません。
授乳間隔を空けすぎないことは、ママの乳腺炎を防ぐためにも大切です。胸のしこりや張りがあるときは、こまめに授乳をして乳腺炎を防ぎましょう。
胸に強い痛みがあったり38.5度以上の高熱が出ていたりする場合は、乳腺炎が悪化している証拠です。早めに医療機関や助産所に相談してください。
起こしてあげるときは優しく
赤ちゃんがぐっすり眠っているときは、優しく起こしてから授乳しましょう。ゆさぶったり大きな音を立てたりすると、赤ちゃんが驚いてしまいます。
まずは名前を呼び「おっぱいだよ」と優しく声をかけましょう。その後、足裏を軽くもんだりくすぐったりして刺激すると、快適に目覚めやすくなります。
授乳前におむつを替えたり、顔をガーゼで優しく拭いてあげたりすると自然に目が覚めることもあります。
新生児がよく寝ることについてよくある質問
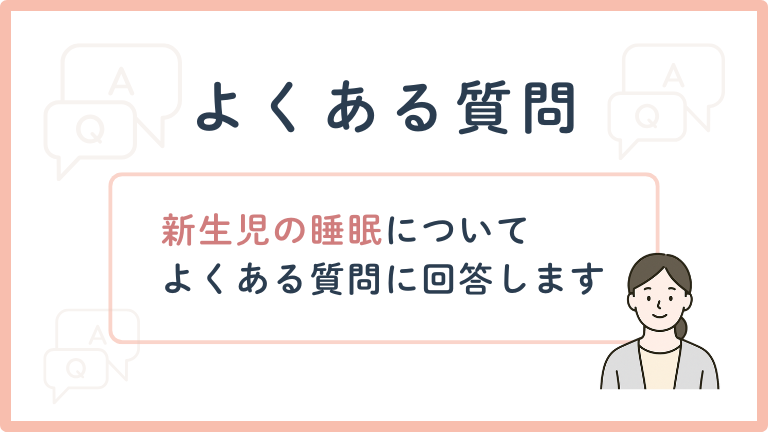
ここでは、新生児の睡眠について、よくある質問にお答えします。
日中はよく寝ているのに夜はあまり寝ない場合、どうすればいい?
新生児は昼夜の区別がついていません。生後2〜3ヵ月頃までは、日中はよく寝て夜に起きてしまうことがあります。
よくあることなので、赤ちゃんの睡眠リズムが自然に整うのを待つようにしましょう。
夜あまり寝てくれないことに悩んでいる場合は、寝る環境を工夫してみてください。
昼間は部屋を明るくし、夜は暗く静かにすると昼夜の感覚を少しずつ覚えていくでしょう。成長とともに睡眠のリズムが整い、生後6ヵ月頃には昼夜の区別がはっきりとついてきます。
母乳なのによく寝る場合、母乳は足りている?
母乳はミルクよりも腹持ちがよくないはずなのに、母乳でよく寝ていると心配になるママもいるでしょう。
確かに、母乳はミルクよりも消化が良いため、睡眠時間が短くなる傾向にあると言われています。
しかし、母乳やミルクをよく飲めていておしっこ・うんちがいつも通りに出ていれば、母乳は足りていると考えられます。赤ちゃんはお腹が満たされるとよく眠るものです。
万が一いつも通りに母乳を飲めていない上に、赤ちゃんの具合が悪そうであれば早めに受診してください。
ミルクを足したらよく寝るようになったけど、寝かせすぎて平気?
新生児期は、授乳間隔が空きすぎないよう注意してください。ミルクは母乳よりも腹持ちがよいので、お腹が空かない赤ちゃんは長く眠ることがあります。
しかし授乳間隔が空きすぎると、脱水症状や低血糖が起こる可能性があります。
4時間以上眠っている場合は、優しく起こして授乳しましょう。
二人目はよく寝るって本当?
二人目の赤ちゃんのほうがよく寝ると感じるママもいます。
一人目で育児経験があるママはお世話に慣れているため、赤ちゃんは安心して眠りやすいのかもしれません。また、上の子の声や生活音に慣れて育つことで、多少の音では目を覚ましにくくなることもあります。
もちろん個人差もあるため「二人目なのに寝てくれない」と不安になる必要はありません。赤ちゃん一人ひとりのペースで成長していきます。
うつ伏せだとよく寝るけど安全?
新生児を意図的にうつ伏せにするのは控えてください。
うつ伏せ寝はお腹の中にいたときの姿勢に近く、赤ちゃんが落ち着いて眠りやすい体勢です。
しかし、乳幼児突然死症候群(SIDS)のリスクを高めるとされています。SIDSとは、赤ちゃんが眠っている間に突然亡くなってしまう原因不明の病気です。
うつ伏せ寝は、顔が寝具に埋もれてしまい窒息する危険もあります。まくらやタオル、ぬいぐるみも赤ちゃんの顔まわりには置かないでください。
赤ちゃんの安全を守るために、1歳になるまでは仰向けに寝かせましょう。
心配しすぎず、赤ちゃんの様子を見守ろう
赤ちゃんがよく寝るのは、からだや脳の発達に欠かせない成長の過程です。特に昼夜の区別がつかない新生児期は、日中でも夜間でも長く眠ることがあります。
赤ちゃん一人ひとりによって、睡眠や授乳のリズムは異なります。初めての育児では戸惑うこともあると思いますが、心配しすぎず赤ちゃんの成長をあたたかく見守っていきましょう。
Midmama公式インスタグラムのご案内

\ 助産師視点で信頼できる情報を発信中! /