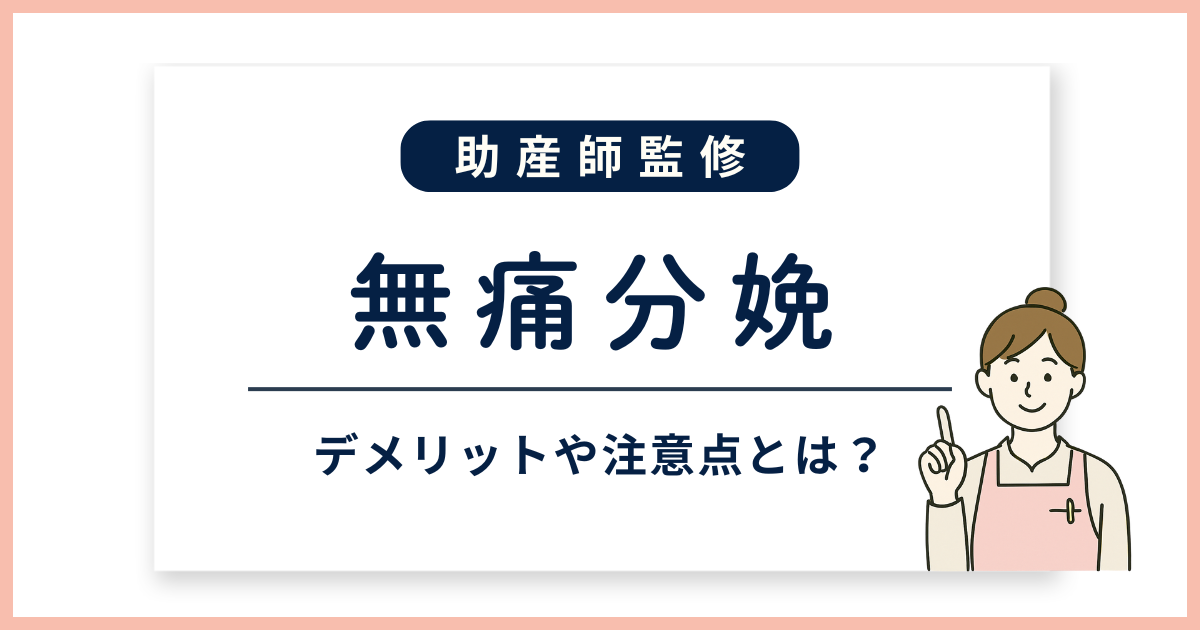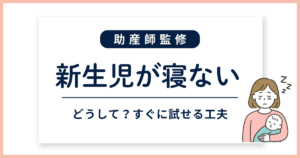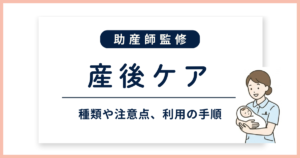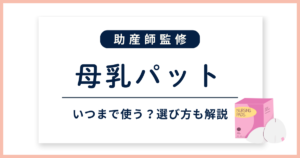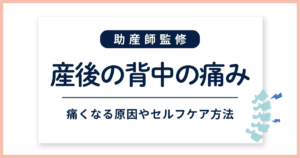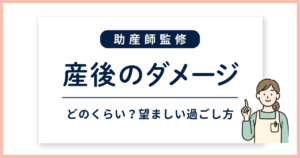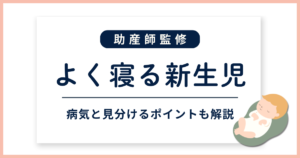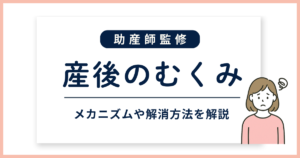無痛分娩は、麻酔を使って陣痛の痛みを和らげながら出産する方法です。
無痛分娩に「ラクな出産ができるかも」というイメージを持つ人も多いのではないでしょうか。
しかし実際には、分娩時間が長引いたり合併症が生じたり、特に赤ちゃんには望ましくない影響が出てしまうこともあります。
この記事では、無痛分娩について知っておきたい注意点を解説します。
ママと赤ちゃんそれぞれのメリット・デメリットをしっかり理解しておきましょう。
そもそも無痛分娩とは?

無痛分娩とは、麻酔薬を使用して陣痛を和らげながら出産する方法です。
一般的には「硬膜外麻酔(こうまくがいますい)」で背中に細い管を入れたのち、麻酔薬を注入する方法で行われます。
麻酔が神経の働きを抑えることで、痛みを感じにくくする仕組みです。
日本における無痛分娩の普及率は3割程度(※1)といわれています。
近年、無痛分娩に対応する施設は急速に増えているものの、まだ一般的とはいえません。
地域によって対応できる施設の数にも差があります。
※1:厚生労働省|第8回「妊娠・出産・産後における妊産婦等の支援策等に関する検討会」議事録
無痛分娩の方法
無痛分娩は、大きく2つに分類されます。
- 計画無痛分娩:あらかじめ日程を決めて行う方法
- 自然陣痛後の無痛分娩:自然に陣痛が始まってから麻酔を使う方法
病院によって対応している方法は異なります。
計画無痛分娩のみに対応し、自然陣痛後の無痛分娩には対応しない病院も少なくありません。
計画無痛分娩
計画無痛分娩は、あらかじめ出産日を決めておき、予定日に麻酔と陣痛促進剤を用いてお産を進める方法です。
出産のスケジュールを立てられるため、家族の予定に合わせたい人や立ち会い出産を希望する人にとっては、計画的に準備ができるメリットがあります。
計画無痛分娩のデメリットは、お産がなかなか進まないことがある点です。
陣痛は、ママと赤ちゃんの準備が整ったタイミングで、本来自然に訪れるものです。
そのため、人工的に陣痛だけを起こしても、子宮口がうまく開かなかったり、赤ちゃんが降りてこなかったりすることがあります。
計画無痛分娩だからといって、すべてが想定どおりに進むとは限らない点は理解しておきましょう。
自然陣痛後の無痛分娩
自然陣痛後の無痛分娩とは、赤ちゃんの準備が整い、自然に陣痛が始まってから麻酔を注入する方法です。
「できるだけ自然な流れで出産したい、でも痛みは軽くしたい」と考える方にとっては、理想的な手段となるでしょう。
しかし、お産のペースが早いと麻酔が間に合わないこともあります。
特に経産婦の場合はお産のペースが早い傾向にあるため、麻酔が効き始める前に赤ちゃんが生まれることもあります。
また、無痛分娩に24時間対応している施設は限られます。
「対応できる」としていても、実際には月に数回、麻酔科医が不在になる病院もあります。
医師の勤務状況と分娩のタイミングが重なると、希望どおりに無痛分娩できないケースもあるので知っておきましょう。
無痛分娩のメリット

無痛分娩のメリットと聞いて思い浮かぶのは、陣痛の強い痛みを緩和できることでしょう。
また、持病がある場合は、希望に関わらず医師から無痛分娩を推奨されることもあります。
ここからは、無痛分娩のメリットをママ・赤ちゃん、それぞれの視点で詳しく解説します。
痛みや不安を軽減できる
無痛分娩の大きなメリットは、痛みが軽減しリラックスして出産に臨みやすくなることです。
出産前から痛みに対し恐怖心がある方にとっては、不安も軽くなるでしょう。
痛みがやわらぐことで体力の消耗が少なくなり、産後の回復がスムーズになる人もいます。
妊娠高血圧症や心臓、肺に持病がある人には、医師から無痛分娩を勧めることもあります。
強い痛みを感じると、血管は収縮しやすくなり、心臓や肺に負担がかかってしまうためです。
すべての人に同じ効果が得られるとは限りませんが、痛みに不安がある方や持病がある方にとっては、無痛分娩が選択肢のひとつになります。
赤ちゃんに酸素が届きやすい
陣痛によって強い痛みがあると、痛みに対するストレスホルモンの影響で、ママの血流が悪くなり赤ちゃんに酸素が届きにくくなります。
また、痛みに耐えるために、呼吸が浅くなったり止めたりしがちです。
しかし、麻酔によって痛みが緩和されると、血管の収縮を抑えられ、呼吸も安定しやすくなり、結果として赤ちゃんに届く酸素の量が保たれやすくなります。
ただし、正常な妊娠経過であれば、痛みによって赤ちゃんへ送られる酸素の量が多少減ったとしても大きな問題にはなりません。
つまり「無痛分娩を選ぶことによって赤ちゃんに良い影響がある」というよりは、ママの状態を安定させることで間接的に赤ちゃんへの負担を減らせると捉えるのがよいでしょう。
参考:一般社団法人 日本産科麻酔学会丨Q13. 硬膜外無痛分娩のメリットはなんですか?
無痛分娩で起こりうるリスク

これまで解説したように、無痛分娩にはさまざまなメリットがあります。
痛みが和らぐことで心身の負担を軽減できますが、実はメリットばかりではありません。
特に赤ちゃんにとっては、かえって負担になることもあります。
無痛分娩のリスクについても理解を深めましょう。
足の力が入りにくくなる
麻酔は痛みを感じる神経だけでなく、動きや感覚に関わる神経に作用することもあります。
そのため、いきみたい感覚が分からなくなり、お産がスムーズにいかなくなることがあるのです。
たとえ助産師がいきむタイミングを教えてくれたとしても、足に力が入らなければうまくいきめません。
一般的には麻酔が切れれば自然と回復しますが、個人差があります。
分娩が長引いて赤ちゃんに負担がかかる
麻酔の影響により陣痛が弱くなったり、いきみにくくなったりすると、お産が長引くことがあります。
また、お産に時間がかかると、赤ちゃんへの負担が増えてしまいます。
特に計画無痛分娩では、陣痛促進剤によって子宮の収縮が収縮しすぎることで、赤ちゃんへ酸素が十分に行き届かず、赤ちゃんが苦しくなるおそれもあります。
かゆみが生じることがある
もともと皮膚が弱い人はかゆみが起こることもあります。
麻酔を入れる細い管が背中の皮膚を軽く圧迫し、炎症が生じやすくなるためです。
特別な治療は必要ありませんが、我慢できないときは薬で対応することもあります。
尿が出にくくなることがある
麻酔の影響で膀胱の感覚が鈍くなると、尿意がわかりづらくなります。
産後に尿が溜まった状態が続くと子宮の戻りを妨げてしまうため、自分でうまく出せないときはスタッフが細い管(カテーテル)を入れて尿を出さなければなりません。
多くのママは退院するまでに自然と感覚が戻りますが、麻酔によって神経の働きが抑えられているため時間がかかる人もいます。
また、スタッフによる処置が必要になると、育児練習できる時間が短くなってしまったり、思ったように休む時間を取れないこともあります。
血圧が低下することがある
背中の神経は、血圧の維持にも関わっています。
そのため、無痛分娩のための麻酔によって神経の働きが抑えられると、血管がゆるみ血圧が下がってしまいます。
ほとんどの場合は心配ない程度ですが、まれにママの気分が悪くなったり、赤ちゃんが苦しくなったりすることがあります。
こうした事態を考え、病院では血圧をこまめにチェックし、緊急時にはすぐ対応できるような体制が義務付けられています。
吸引・鉗子(かんし)分娩になることがある
吸引分娩や鉗子分娩は、赤ちゃんを早く出す必要があるときに行われます。
専用の器具を使って分娩を助ける方法で、赤ちゃんに以下のようなリスクを伴います。
| 吸引分娩 | 鉗子分娩 | |
| 方法 | 赤ちゃんの頭に吸盤のようなカップを装着し、 引っ張ることでお産を助ける | トングのような「鉗子」で赤ちゃんの頭をはさみ 引き出す |
| 軽度のリスク | 赤ちゃんの頭に産瘤(こぶのようなもの)が できやすくなる | 顔に軽い傷がついたり 跡が残ったりすることがある |
| 重大なリスク | 骨折、帽状腱膜下血腫 | |
産まれたばかりの赤ちゃんに傷やこぶがあると驚くかもしれませんが、ほとんどは数日で消えるため、心配しすぎる必要はありません。
ただし、帽状腱膜下血腫(ぼうじょうけんまくかけっしゅ)のような重大な病気を引き起こすおそれもあります。
帽状腱膜下血腫とは、骨膜と頭蓋骨の間に血がたまる状態です。
貧血や出血ショックを引き起こし、最悪の場合は命に関わることもあります。
赤ちゃんの発達に影響する可能性もある
一部の研究(※2)で「無痛分娩で硬膜外麻酔を受けて生まれた子どもは、3歳までの発達に影響が出るかもしれない」と報告されています。
ただし、無痛分娩が直接的な原因であると断定されているわけではありません。
母体の年齢や出産の経過なども影響すると言われるため、明らかに否定もできないのが現状です。
※2:Association of epidural analgesia during labor with neurodevelopment of children during the first three years: the Japan Environment and Children’s Study – PubMed
無痛分娩でまれに起こる重篤な合併症
慎重に行われる無痛分娩ですが、ごくまれに合併症が起こることがあります。
確率は低いものの、万が一に備えて重篤なリスクについても把握しておきましょう。
硬膜穿刺後頭痛
「硬膜穿刺後頭痛(こうまくせんしごずつう)は、脳脊髄液が漏れてしまうことで生じる頭痛です。
麻酔の針が誤って硬膜(脊髄を保護する膜)を突きぬけることで起こり、無痛分娩の約1%の確率で生じるとされています。
- 頭痛
- 吐き気
- 首の痛み
硬膜穿刺後頭痛では、起き上がると強くなり、横になると軽くなる点が特徴です。
ほとんどは1〜2週間で自然に回復するため、鎮痛薬を使いながら安静に過ごして様子をみます。
ただし、頭痛や吐き気が続いたり物が二重に見えたりする場合は、特別な処置を行うこともあります。
局所麻酔薬中毒
局所麻酔薬中毒とは、麻酔薬が血管内に入ることで、脳や心臓に強く作用してしまう状態です。
硬膜外腔は血管が多い上に、妊娠中は血管がふくらみやすく、普段よりも薬が血管に入るリスクが高いとされています。
硬膜外腔へ入れるはずの管が血管に入ってしまったり、短い間に大量の麻酔が吸収されたりすると、局所麻酔薬中毒を生じます。
- 耳鳴り
- 舌のしびれ
- めまい、気分の悪さ
- けいれん
- 意識を失う
- 不整脈
けいれんや不整脈が起きると 、命に関わる危険もあります。
硬膜外血腫
硬膜外血腫(こうまくがいけっしゅ)とは、麻酔を入れる空間に、血のかたまりや膿がたまって神経を圧迫してしまう状態です。
しびれや力の入りにくいなどの神経障害が起こります。
発生頻度は数万件に1件(※3)とごくまれですが、適切な処置が遅れると後遺症が残ることもゼロではありません。
万が一生じた際は、手術で血のかたまりや膿を取り除く治療が行われます。
※3:一般社団法人 日本産科麻酔学会丨Q14. 硬膜外鎮痛の副作用が心配です。
全脊髄くも膜下麻酔
硬膜外腔に投与するはずの麻酔薬が、誤って「くも膜下腔」に入ってしまうことで起こります。
約4,000人に1人に起こる合併症です。
くも膜下腔に麻酔が入ると効果が強くあらわれ、血圧が急激に低下してしまいます。
重症化すると、呼吸が止まったり意識を失ったりと命にかかわる恐れも否定できません。
全脊髄くも膜下麻酔は、どんなに注意深く観察していても、予測して防ぐことは難しいとされています。
万が一発生したらすぐに集中治療が必要となるため、無痛分娩を希望する場合は体制の整った病院を選ぶことも重要です。
無痛分娩の注意点

無痛分娩は完全に痛みをなくせるわけではありません。
思ったように痛みが緩和されないケースや、予定どおりに出産に進まないケースもあります。
「無痛分娩を選ばなければよかった…」と後悔するママもいるため、注意点を知っておきましょう。
痛みがゼロになるわけではない
無痛分娩では、あえてすべての感覚を取り除かないようにしています。
完全に痛みをなくしてしまうと、いきむ力が入りづらくなり、お産が長引いてしまうことがあるためです。
また、麻酔を入れるまでは陣痛を伴います。
誤解を生まないために「和痛分娩」と表現する病院もありますが、どちらも内容は同じです。
お産が計画どおりに進まないこともある
計画無痛分娩は予定どおりに進められるイメージがありますが、実際には想定外の進み方になることもあります。
お産の進行が遅くなるだけでなく、反対に早まりすぎて麻酔が間に合わないケースもあります。
理想どおりに進むとは限らないことを十分に理解し、リスクも踏まえて選択することが大切です。
無痛分娩に関してよくある質問

ここからは、無痛分娩に関してよく寄せられる質問に回答します。
なぜ初産で無痛分娩に対応していない病院もあるのですか?
無痛分娩に対応していても、初産婦さんには行わない病院もあります。
理由は施設ごとに異なるものの、主な要因としては以下が挙げられます。
- お産の予測が難しい
- 病院側の体制に限りがある
お産が長引くと、吸引分娩や鉗子分娩、帝王切開が必要になるケースもあるため、安全面を考えて、お産が比較的スムーズに進みやすい経産婦さんを優先する病院もあります。
また、無痛分娩をするためには、麻酔科医の常駐や緊急時にすぐ対応できる体制が欠かせませんが、病院によっては麻酔科医が不在の時間帯もあります。
できるだけリスクを減らすために、対象を経産婦さんに絞っている病院もあるようです。
無痛分娩の費用はどのくらいですか?
無痛分娩の費用は、地域や病院によって大きく異なります。
一般的には、自然分娩の費用に5万〜15万円程度を上乗せした費用が相場です。
土日祝日や夜間の対応には、追加料金がかかる病院もあります。
出産には出産育児一時金(50万円)が支給されますが、無痛分娩を希望すると自己負担が10万円以上になることもあります。
実際の金額は病院によって違うため、事前に確認しておきましょう。
無痛分娩しなければよかったと後悔する理由は何ですか?
無痛分娩を経験したママの中には「思っていたのと違った」と後悔する人もいます。
よくある理由は以下のとおりです。
- 計画しても、出産が予定どおりに進まなかった
- 麻酔をしても、思ったほど痛みが減らなかった
- 費用の負担が大きい割に、あまり効果がなかった
無痛分娩はメリットがある一方で、必ずしも期待どおりの効果が得られるとは限らないことを理解しておくことが大切です。
無痛分娩で死亡した例があるのですか?
過去に無痛分娩のあとに亡くなった方がいます。
日本産婦人科医会の調査(2010年〜2023年)によると、出産に関連して亡くなった妊産婦さん590名のうち、無痛分娩を受けていた人は24名、うち23名は陣痛促進剤を用いた計画無痛分娩でした。
| 病名 | 説明 | 人数 |
| 羊水塞栓症(ようすいそくせんしょう) | 羊水が血液中に入り、心臓や肺の動きが悪くなる | 17名 |
| 子宮破裂・産道裂傷 | 子宮が破ける・産道が裂けることで出血を起こす | 3名 |
| 大動脈解離 | 大動脈の壁が裂け、出血をおこす | 1名 |
| くも膜下出血 | 脳の血管が破れて出血をおこす | 1名 |
| 麻酔が直接関係したトラブル | 誤って脊髄の近くに入った、または効きすぎて中毒症状がおきた | 2名 |
| 合計 | 24名 | |
参考:妊産婦死亡症例検討評価委員会・日本産婦人科医会|母体安全への提言 2023
上記で原因となっている病気は通常であれば強い痛みを伴うため、麻酔の効果がなければ迅速な治療ができたかもしれません。
「痛み」はからだの異常を知らせる大事なサインです。
痛みが弱まることでトラブルの発見が遅れるリスクがあることは、十分に理解しておく必要があります。
安全性を確認して自分に合う方法を選ぼう
無痛分娩は痛みを和らげ、ママのからだやこころの負担も軽減する手段のひとつです。
しかし、分娩が長引いて赤ちゃんに負担がかかったり、まれに重い合併症が起こったりするリスクもあります。
自分に合う方法を選ぶためには、メリットだけでなく注意点やリスクも十分に理解することが大切です。
納得のいくお産を迎えられるように、医師や助産師とよく相談して出産方法を決めましょう。